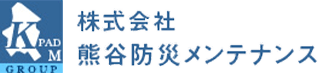各建物の点検 INSPECTION

- トップページ
- 各建物の点検
FIRE EQUIPMENT 消防用設備等の点検と報告
-

定期点検報告制度
~消防法 第17条の3の3~消防用設備および特殊消防用設備は、火災が発生した際に確実に機能を発揮することが求められます。そのため、消防法では、これらの設備を設置している防火対象物の関係者に対し、定期的な点検と、その結果を消防長または消防署長に報告する義務が定められています。
点検・報告義務のある人 防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など) 点検をする人 消防設備士・消防設備点検資格者など 点検の内容と点検期間 機器点検:6カ月ごと
総合点検:1年ごと点検結果の報告 特定防火対象物:1年に1回
非特定防火対象物:3年に1回 -
消防法 第17条
(消防用設備等の設置、維持義務等)学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める技術上の基準に従つて、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならない。
-
消防法 第17条の3の3
(消防用設備等についての点検及び報告)第17条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
FLOW 点検および報告の流れ
-
STEP01 書類を確認し現地調査
設計図書や過去の点検報告書などを用いて、設備や数量を確認します。
さらに、必要に応じて現地での調査も実施いたします。
-
STEP02お見積り
設備や数量等に応じてお見積りを作成します。
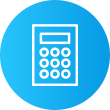
-
STEP03事前のお打合せの実施
点検スケジュールの調整をし、点検項目のご説明をします。

-
STEP04点検の実施
【機器点検 6ケ月ごと】
消防用設備の機能について、「外観」や「簡単な操作で確認できる事項」を法令基準に基づき点検します。
【総合点検 1年ごと】
消防用設備を実際に作動させ、総合的に正常な機能が維持されているかを法令基準に従って点検します。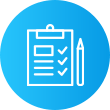
-
STEP05整備の実施
不良個所が発見された場合
点検結果を詳細にご報告いたします。
また、設備の更新(リニューアル)が必要な場合には、別途ご提案させていただきます。
-
STEP06点検結果のご報告
点検結果についてはご報告いたします。
また、設備の更新(リニューアル)が必要な際には、別途ご提案いたします。
-
STEP07所轄消防署へ定期報告
防火対象物の関係者は、所定の期間ごとに管轄の消防署長へ点検結果の報告書を提出する必要があります。
飲食店や店舗などの特定防火対象物は1年に1回、事務所や共同住宅などの非特定防火対象物は3年に1回の報告が義務付けられています。
LIST よくある不良項目
こんな状態になってたら
すぐに改修しましょう
-

消火器
消火器本体のサビや腐食、本体部品の欠損や変形。
-

屋内消火栓設備&
スプリンクラー操作の障害になるものを置くことはNGです。ホースやポンプ、バブルの劣化水漏れなど。
-

自動火災報知設備
操作の障害になるものを置く
ことはNGです。 -

誘導灯
誘導灯の電球切れやプレートの破損。
-

連結送水管
耐圧試験を行っていない。
WORKS 防火管理者の仕事って?

火災の予防と適切な防火対策の確立・実施を担う防火管理業務は非常に重要です。消防法では、一定の規模以上の建物に対し、防火管理者(有資格者)を選任し、必要な防火管理業務を実施させることが義務付けられています。各事業所の管理職または監督職にある方で、防火管理者講習を修了した方が防火管理者として任命されます。
防火管理者が必要な建物について
- 店舗、ホテル、病院など、多くの不特定多数が利用する建物(特定防火対象物)のうち、建物全体の収容人数が30人以上のもの。
- 火災時に自力避難が非常に困難な方が入所する社会福祉施設などの建物(避難困難施設)で、収容人数が10人以上の建物。
(平成21年4月1日から適用) - 倉庫、事務所、共同住宅、学校、工場などの建物(非特定防火対象物)のうち、収容人数が50人以上の建物。
- 新築工事中の建物で、収容人数が50人以上の一定規模以上の建物。
- 建造中の旅客船で、収容人数が50人以上かつ甲板数が11以上の建物。
防火管理者資格の区分と取得方法について
防火対象物の用途や規模、収容人数に応じて、甲種または乙種防火管理者の講習が設けられています。甲種防火管理者の資格は2日間の講習、乙種防火管理者の資格は1日間の講習を修了することで取得可能です。
※詳しくは各消防署へお問い合わせ下さい。
FLOW 防火管理者の業務と実務フロー
-
STEP01消防計画の作成
-
STEP02消火、通報および避難訓練の実施
-
STEP03消防設備や消防用水、消防活動に必要な設備の点検および維持管理
-
STEP04火気の使用および取扱いに関する監督
-
STEP05建造中の旅客船で、収容人員が50人以上かつ甲板数が11以上のもの
-
STEP06収容人員の管理
-
STEP07その他の防火管理に必要な業務